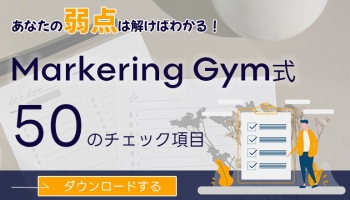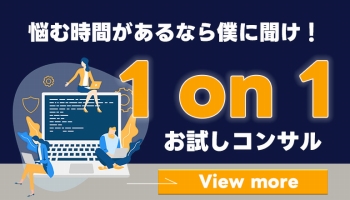マーケティング担当者やマーケティングに興味がある方がよく耳にする「(顧客)インサイト」。
ニーズやウォンツなら聞いたことがあるけど、インサイトって何?と思っているあなたに、インサイトとは何か、顕在ニーズや潜在ニーズとの違いについて解説していきます。
また、インサイトの見つけ方からインサイトの活用事例も併せて紹介していきますので、あなたの新たな知識となれば幸いです。
顧客インサイトとは?その重要性
顧客インサイトとは、顧客自身も自覚していない、あるいは言葉にできないような深層心理にある本音や動機、隠れた欲求を指します。
単に「ニーズ」と呼ばれる顕在的な要求よりもさらに深く、顧客の行動を根本的に動かす「なぜ」の部分を洞察することで得られるものです。
「消費者インサイト」と表記されることもありますが、意味は同じです。
現代はモノや情報が溢れる時代であり、顧客のニーズは多様化し、表面的なニーズだけでは商品やサービスが売れにくくなっています。
このような状況において、顧客インサイトを把握することは、以下のような点で極めて重要です。
真に求められる商品
サービスの開発: 顧客自身も気づいていない本質的な欲求を満たす商品やサービスは、顧客に「これだ!」と感じさせ、強い共感を生み出し、競合との差別化につながります。
効果的なマーケティング戦略の立案
顧客インサイトを理解することで、顧客に響くメッセージやコミュニケーション手法を考案できます。顧客の「買う気スイッチ」を押し、購買行動を促すことが可能になります。
顧客ロイヤルティの向上: 顧客の深層心理を理解し、期待を超える価値を提供することで、顧客との強固な信頼関係を築き、長期的な顧客ロイヤルティの向上に貢献します。
顧客インサイトとニーズ・潜在ニーズとの違い
顧客インサイトは、よく「ニーズ」や「潜在ニーズ」と混同されがちですが、以下のような違いがあります。
顕在ニーズ
顕在ニーズとは、顧客自身が認識しており、明確に言葉にできる欲求を指します。
例えば、「新しいスマートフォンが欲しい」「時短できる調理家電が欲しい」など。
潜在ニーズ
一方、潜在ニーズとは、顧客自身ははっきりとは認識していないが、無意識に求めている欲求を指します。
例えば、「家事の時間を短縮して、家族との時間を増やしたい」といった漠然とした願望など。
顧客インサイト
顧客インサイト(消費者インサイト)とは、潜在ニーズよりもさらに深く、顧客自身も自覚していない無意識の感情や動機、行動原理を指します。
なぜ潜在ニーズが生まれるのか、その根本にある「なぜ」に迫るものです。
例えば、「家事に時間をかけたくないのは、単に楽をしたいからではなく、家事以外の時間に充足感を得たいという自己実現欲求があるから」といったような深層心理です。
顧客インサイトを見つける方法
顧客インサイトを見つけるには、多角的な視点と深い洞察力が必要です。
一般的な方法は以下の通りです。
データ収集
まずはデータ収集です。データ収集方法には以下が挙げられます。
アンケート・インタビュー
顧客への直接的な質問を通じて情報を集めます。
ただし、顧客自身がインサイトを言語化できるとは限らないため、「なぜそのように感じるのか」「具体的にどのような状況か」など、深掘りする質問が重要です。
特に、一対一のデプスインタビューは深層心理を探るのに有効です。
行動観察調査
顧客が実際に商品やサービスを利用している様子、店舗での行動などを観察します。言葉にならない行動からインサイトを発見できることがあります。
SNS分析(ソーシャルリスニング)
SNS上の口コミや投稿、レビューなどを分析し、顧客のリアルな感情や意見、傾向を把握します。自発的な発言からインサイトが見つかることがあります。
購買履歴・Webサイト閲覧データなどの定量データ分析
顧客の属性データや購買データ、Webサイトでの行動データなどを分析し、数値的な傾向からインサイトにつながる仮説を立てます。
投影法(コラージュエクササイズなど)
写真やイラストなどを使って顧客に自由に表現してもらい、言葉にしにくい感情やイメージを引き出す手法です。
データ分析と仮説構築
続いてはデータ分析と仮設構築です。
収集したデータを表面的に捉えるだけでなく、なぜそのような行動や発言があったのかを深く考察します。
ペルソナ設定
顧客の年齢、性別、職業、趣味、価値観など、詳細なプロフィールを設定し、具体的な顧客像をイメージします。
共感マップ
顧客が「見ているもの」「聞いているもの」「考えていること・感じていること」「言っていること・やっていること」などを可視化し、顧客の置かれている状況や感情を深く理解します。
カスタマージャーニーマップ
顧客が商品やサービスを知ってから購入、利用に至るまでのプロセスを可視化し、各段階での顧客の感情や思考の変化を把握します。
定性データと定量データの統合
定性データから得られた仮説を定量データで検証したり、定量データから見つかった傾向を定性データで深掘りしたりすることで、より精度の高いインサイトを発掘します。
多角的な視点での分析
一つの情報源に固執せず、複数の視点からデータを分析し、矛盾点や意外な発見に目を向けます。
「なぜ」を深掘りする質問
「便利だから」ではなく「なぜ便利だと感じるのか」「その便利さによって何が解決されるのか」といった問いを繰り返すことで、本質的な欲求に迫ります。
インサイトの検証と活用
発見したインサイトが本当に顧客の行動を動かす要因となっているのか、さらなる検証を行います。
検証されたインサイトを基に、商品開発、広告宣伝、プロモーション、顧客サポートなど、企業活動のあらゆる側面に反映させます。
インサイトは常に変化する可能性があるため、定期的な見直しと再分析が必要です。
顧客インサイト活用事例
顧客インサイトを活用した事例をいくつかご紹介します。
大手企業様ばかりですが、顧客インサイトの活用のイメージはつきやすいと思いますのでご参考ください。
日清食品「カップヌードルリッチ」
高齢層の「健康志向だからカップ麺を食べないわけではなく、おいしければ食べたい」というインサイトを見抜き、高級感や素材にこだわった商品を開発し、新たな顧客層を開拓しました。
フォルクスワーゲン「Think small.」
当時主流だった大型車ではなく、小型車の「フォルクスワーゲン」を販売するにあたり、「小さいことは恥ずかしい」という顧客の意識がある中で、「小さいことが良いことである」というインサイトを捉え、自虐的ながらもユーモラスな広告で成功しました。
カリフォルニア牛乳協会「Got Milk?」キャンペーン
牛乳の消費量が落ち込む中、「クッキーやパンを食べる時に牛乳がないと寂しい」というインサイトを発見し、牛乳売り場だけでなく、クッキーやパンの売り場付近に「Got Milk?」(牛乳、買った?)という広告を出すことで、牛乳の消費を促進しました。
顧客インサイトの発見と活用は、単なる表面的なニーズに応えるだけでなく、顧客の心に深く響く価値を提供し、企業と顧客のより良い関係を築くための重要な鍵となります。